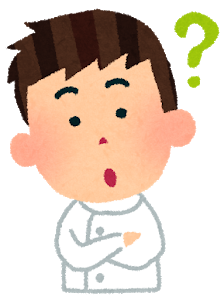こんにちは!なおです!
このブログでは『心を軽くする考え方』『医療』『リハビリ』の3つを柱に情報発信を行っています。
ブログを通しあなたの人生を少しでも良い方向に変えていけるような“お手伝い”が出来るようになることが最大の目標です!是非、参考にして頂きながら今よりも良い毎日を歩んで下さい!
そんな悩みを持たれている作業療法士の方や実習生さんも多いですよね!
今回は、時短テクニックとしてカルテから効率よく情報収集していくコツをこの記事を読んでくれている方だけにお伝えして行きます!
是非、この記事を活用・参考に情報収集をしてみて下さい。
情報収集が苦手。克服する5つの方法を紹介|作業療法士・実習生必見

では早速、情報収集の苦手を克服する5つを紹介して行きたいと思います!
・全ての情報を初回で取ろうとしない
・極力メモを取らない
・疾患の勉強を事前しておく
・分からなければ同僚や上司に聞く
・看護師さんに状態を聞く
です。
1つずつ具体的に解説して行きます!
重要なことも記述しますので見落としのないようにしてみて下さい!
全ての情報を初回で取ろうとしない
情報収集の苦手を克服する方法として、全ての情報を初回で取ろうとしないようにして下さい!
片っ端から情報収集する必要はありません!
片っ端から情報収集をしていては終わるものも終わらなくなります。
カルテというものは『初回に必ず取らなければならないもの』と『2回目以降でも良い情報』というものが全て載っています。
それを見極めず無闇矢鱈に情報を拾おうとするから莫大な時間が掛かってしまうんです。
『初回に必ず取らなければならないもの』だけ確実に抜き取ることが出来れば、あとは初回介入が終わってからゆっくり情報収集すれば良いんです。
では、その『初回に必ず取らなければならないもの』というのは何なのか?
以下のものになります!
・現病歴
・既往歴
・安静度
・リスク管理しなければならないもの
・検査所見
のみです。
これだけ確実に抜き出せれば患者さんの元へGoです!
あとは実際に自分で評価したり患者さんとコミュニケーションを取り情報の肉ずけをしていけばOKです。
それでも足りない情報があれば時間の余裕があるときにカルテから探しでせば良いんです。
不安だからと言ってお守り変わりのように全ての情報を抜き出していては時間がいくらあっても足りません。
効率よくやっていくには、その都度、その都度優先順位の高い情報だけ抜き出して行動出来るようにして行きましょう!
極力メモを取らない
情報収集の苦手を克服する方法として、極力メモを取らないようにしてみましょう。
メモを取るメリットは精神的な安心感を手に入れられることです。
メモを取るデメリットは
・カルテからの情報を書き写すのに時間が掛かる
・書き出したメモの中から必要な情報を見つけ出すのに時間が掛かる
・情報が更新される為にメモが必要になる
・書き出すだけで疲れてしまう
・メモをなくしてしまうかもしれないリスクを背負う
です。
もし仮にメモを取るのなら必要最低限のことだけメモって患者さんの元に行きましょう。
以下の黄色部分がメモ帳だとすれば
中大脳動脈領域脳梗塞 左麻痺
安静度:ギャッチUP40°まで
禁忌:左上肢血圧測定(透析のためのシャントがある為)
医師からのコメント:バイタル変動に留意しゆっくりとリハ実施
ぐらいで十分です。これだけ情報があればリハビリは行えます。
本当に必要最低限のものだけメモって患者さんの元に行き、あとは実際に患者さんを診て評価し情報を足して行きましょう!
それが出来れば十分です。
極力メモを省き患者さんを実際に見るようにしましょう!
そうすることによってカルテと睨めっこしている時間も無くせますよ!
疾患の勉強を事前しておく
情報収集の苦手を克服する方法として、疾患の勉強を事前にしておきましょう!
事前に疾患の勉強しておくことで疾患特有の症状やリスクを始めから把握しておくことが出来ます。
事前に勉強しておくべき疾患として
・病院、施設が受け入れることが多い疾患
・一般的に多い疾患
のみで良いです。
評価するポイントや気をつけなければならない点も分かる為、あとは安静度と禁忌、検査データだけ把握すればすぐに患者さんの元にいくことが出来ます。
余裕が出来れば難病や難しい病気の勉強もしておくと病気が分からなく疾患のことから調べ直すということが少なくなり動き始めがスムーズになります。
疾患を正しく理解することは患者さん理解にもつながります。
勉強を怠らず常に知識を蓄えて行きましょう!
分からなければ同僚や上司に聞く
情報収集の苦手を克服する方法として、分からなければ同僚や上司にどんどん聞くようにしましょう。
分からないものを深く考えていても分からないです。
時間も多く使ってしまいますし調べて『これだ!』と思っても100%の自信を持てないまま患者さんに会いに行くことになるかもしれません。
それはリハビリを行なっていくにあたってもリスクになり得ます。
リスクを減らす為にも自分から頭を下げて聞けるようにして行きましょう!
・いらないプライドは捨てる
・1度聞いたことは2回聞かないようにする
・後でしっかりと勉強し直す
・成果を教えてもらった人に返す
・自分が先輩になったときに同じことを後輩にするようにする
これが出来ればバッチリです。
人に頭を下げて物事を聞くことは決して恥じることではありません。
患者さん第一に考えてより安全でより的確なことが出来ればどんな手段を使っても悪いことはありません。
分からなければ同僚や上司に『ちょっとお聞きしたいことがあるんですが』と素直に物事を尋ねられるようにしましょう。
それが情報収集スピードを格段に上げたり効率性をあげたりすることができるようになります。
看護師さんに状態を聞く
情報収集の苦手を克服する方法として、患者さんの状態を看護師さんに聞けるようになることが大切です。
上記に挙げた
・現病歴
・既往歴
・安静度
・リスク管理しなければならないもの
・検査所見
これらを情報収集しまだ不安が残るのであれば最後に頼るのは病棟の看護師さんです。
看護師さん達は常に新しい情報を持ち、医師とも密に情報交換をしていることが多いです。
また、患者さんの一番近くにいるのでカルテに載っている内容より濃い情報を持っていたりします。
なので患者さんに介入する前に日勤担当看護師さんを見つけ『どんな状況ですか?』『日中の様子はどうですか?』と尋ねることが出来るだけで患者さんの情報を詳しく知ることが出来るようになります。
人に聞けるというスキルは格段に情報収集能力を高めてくれます!
ぜひ、恥じることなく患者さんの為だと思って人に物事を尋ねるようにして行きましょう!
情報収集の苦手を克服するには経験を積み上げる

苦手を克服するには苦手に臆することなくぶつかっていくことが大切です。
苦手なものを苦手だと思い、いつまでも現実から目を背けていては上達するものもしません!
苦手なものから目を背けているといつまで経っても苦しいままです。
目を背けることなく苦手を克服するよう意識して行動を積み重ねて行けると必ず情報収集能力は上がって行きます!
1年や2年でサクッと情報収集能力を上げていくのが難しい人もいるかもしれません。
ですが苦手なものっていつまで経っても苦手とは限りません。
苦手意識を持ち苦手なものから目を背けてしまうからこそ苦手なものは、いつまで経っても克服が出来なかったりするんです。
今、克服しようと思い行動出来たのなら確実に苦手を克服する事が出来ます!
コツコツ努力を積み上げて行きましょう!
失敗を試行錯誤し乗り越えていくことで必ず成長して行きます!
苦手から目を背けず向き合っているとその経験から必ず苦手を克服することが出来ます!
情報収集能力を上げることで格段に患者さんの理解能力は深まり良い支援、介入が行えるようになります。
諦めず行動出来た人のところだけに良い事が必ず舞い降ります!
他人よりペースが遅くたっていいんです。自分なりのペースで情報収集能力を上げて行きましょう!
臨床人生長いんです。
ゆっくりとでも確実に成長できるように行動できれば良いんです!
慌てない事が大切!
適切なタイミングで適切な情報収集をしていくのが大切

いかがだったでしょうか!?
情報収集が苦手。克服する5つの方法を紹介|作業療法士・実習生必見と題して記事をまとめて参りました。
始めの方に『初回に必ず取らなければならないもの』と『2回目以降でも良い情報』があると記述しましたが『初回に必ず取らなければならないもの』は患者さんの状態に関する事です。
とにかく患者さんの状態を自分が悪くしないようにする為の情報収集です。
『2回目以降でも良い情報』とは患者さんの本質を知る情報収集です。
家族構成を聞いたり、住んでいる場所を聞いたいり、趣味を聞いたり、日課を聞いたり、今までの人生のことを聞いたり、介護保険のことを聞いたりなど、その人の人柄や生きてきた過程を知る情報収集です。
慌てなくても患者さんの生命には大きく関わらない情報ばかりだと思います。
上記のように使い分けて情報収集を行なっていけば格段に効率性は上がって行きます!
1回で全てを知ろうとしなくて良いんです。少しずつ少しずつ知っていけるように関われると最後には担当患者さんのことはなんでも知っているセラピストになれます。
ぜひ、患者さんに興味を持って接してみて下さい!
それが情報収集能力を格段に上げる為の良いスパイスになりますよ!
以上、本日のブログでした。
最後まで目を通して頂き本当にありがとうございました。
その他にも





などの記事を書いています。気になる記事がありましたら是非、覗いてみて下さい。
少しでもあなたの未来が良い方向に向かうことを祈っています。
『悩み事』『もっと聞いてみたい事がある』と言う方はTwitterのDMやブログのお問い合わせから連絡下さい。1人で悩まず一緒に歩んでいきましょう!